YouTubeやニコニコ動画、Xなどで楽曲を公開している方々の中には、「音楽配信サービスへの登録はまだ」と考えている人も多いのではないでしょうか。特にボカロPやインディーミュージシャンの間では、SNSでの反応を見てからの判断や、「わざわざお金をかけてまで配信する意味があるのか」という疑問を持つことも珍しくないと思います。しかし、音楽制作の目的を考えると、多くの場合「誰かに聴いてもらいたい」という思いが根底にあるはずです。そして、その思いを実現するための手段は年々多様化しています。SNSに投稿するだけが正解なのか、それとも音楽配信サービスも活用すべきなのか。今回はこの問いについて、コストや効果の観点から考えていきます。
近年、配信サービスのハードルは大きく下がり、個人でも手軽にSpotifyやApple Musicなど世界中の音楽プラットフォームにリリースできるようになりました。一方で、「ファンが少ないのに配信する価値はあるのか」「どのくらいの収益が期待できるのか」といった疑問も残ります。そこでSNS投稿と音楽配信それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、音楽活動にとって最適な選択を探っていきましょう。

SNSへの投稿と音楽配信、どっちがいい!?
音楽活動のスタイルとゴール設定
音楽を作る人のスタイルは千差万別ですが、大まかに分けると以下の3つのタイプに分類できると思います。
2. コミュニティ層: SNSやサウンドクラウドなどで特定のコミュニティ内で作品を共有し、フィードバックや交流を楽しんでいる
3.セミプロ/プロ層: より広いリスナー層の獲得や収益化を目指している
どのタイプであっても「誰かに聴いてもらいたい」という思いは共通していますが、どれだけ広く届けたいか、どういった反応を期待するかという点で違いがあります。
特にボカロPやインディーアーティストの多くは、当初は趣味やコミュニティ内での活動からスタートすることがほとんどだと思います。でも作品への反応が良ければ、より広く展開したいと考えるようになるケースが少なくありません。そんな移行期に直面する問題が「音楽配信サービスを利用すべきか」という選択なのです。
SNS投稿の現状とその限界
現在、多くのクリエイターが活用しているのがYouTube、ニコニコ動画、X(旧Twitter)、TikTok、Instagram、SoundCloud……といったプラットフォームです。特にボカロシーンでは、まずこうしたSNSにアップロードして反応を見るというスタイルが定着しています。
SNS投稿のメリット
- コスト面: 基本的に無料で始められる
- 即時性: アップロードするとすぐに公開され、反応も素早く得られる
- コミュニティ: 既存のフォロワーへ直接届けられる
- 拡散性: 良い反応があれば自然と拡散される可能性がある
- ハードル: 技術的な敷居が低く、誰でも気軽に公開できる
しかし、SNSだけに頼った楽曲公開には、いくつかの限界もあります:
SNS投稿の限界
- 一過性: タイムラインの流れが速く、過去の作品は埋もれやすい
- プラットフォーム依存: SNSの方針変更やアルゴリズム変更に左右される
- 収益化の制限: プラットフォームによっては収益化条件が厳しい
- 権利管理: 著作権の明確な管理がしにくい場合がある
- 発見可能性: 音楽を探している新しいリスナーへのリーチが限定的
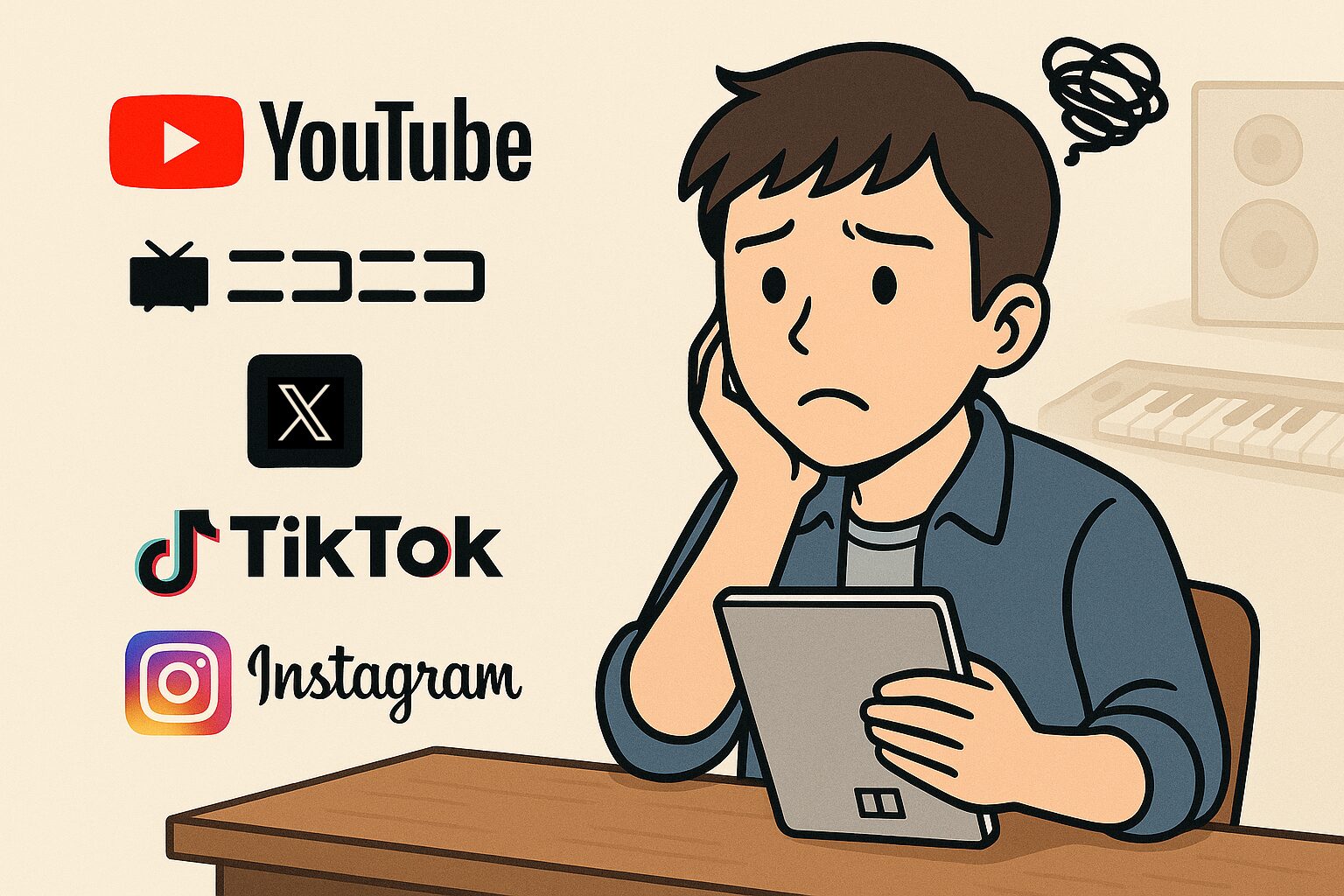
たとえば、YouTubeでの収益化には一定の条件をクリアする必要があり、X(旧Twitter)での楽曲シェアは一時的な注目を集めても、流れて行ってしまうため長期的なリスニング習慣にはつながりにくいという特性があります。
音楽配信サービスの特性と可能性
一方、Spotify、Apple Music、LINE MUSICなどの音楽配信サービスは、音楽を聴くことを主目的としたプラットフォームです。これらのサービスを通じた配信には、以下のようなメリットがあります:
音楽配信のメリット
- グローバルリーチ: 主要なTuneCoreなどのディストリビューターを通じれば、55以上のストアで180カ国以上に配信可能
- 収益化: 再生数に応じた利益が発生する
- 長期的アクセス: プレイリストやライブラリに追加されると長期間聴かれる可能性がある
- 音楽ファンへの訴求: 積極的に新しい音楽を探しているリスナーにリーチできる
- 権利保護: 著作権管理が明確になり、無断使用から保護される
- 二次収益: YouTubeのContent ID登録により、ファンが使用した動画からも収益を得られる可能性がある
もちろん、デメリットもあります:
音楽配信のデメリット
- コスト: ディストリビューターを通じて配信するには費用がかかる
- 手間: 配信用のデータ整備やメタデータ入力など、準備に時間がかかる
- 即時性の欠如: 配信開始までに審査期間があり、即時公開はできない
- 競争の激しさ: 膨大な楽曲の中から発見されるのは容易ではない
こうしたデメリット部分を見て「なんとなく面倒で……」と見送っているケースが多いようです。「結局、SNS投稿と音楽配信のどちらが良いのか」という問いに対する答えは、実は「両方活用する」のがベストである、と思われます。
「どちらか」ではなく「両方」が今の時代の選択肢
SNS投稿と音楽配信は、対立するものではなく補完関係にあります。両方を効果的に組み合わせることで、以下のようなメリットが生まれます。
2.複数の収益源: SNSの広告収入と配信の再生収入という二つの収益源を確保できる
3.相乗効果: SNSで注目を集めた楽曲が配信サービスでも再生されるという循環が生まれる
4.リスナー体験の向上: リスナーが好きな方法で音楽を楽しめる選択肢を提供できる
特に注目すべきは、YouTubeにアップした動画とストリーミングサービスでの配信の関係です。音楽配信サービスに登録すると、YouTube Content IDにも登録され、自分の楽曲が使われている他の動画からも収益を得られる可能性があります。また、Content ID経由の収益化は通常のYouTubeチャンネルの収益化より高いレートになることが多いため、プラスになる要素が大きいのです。

音楽配信サービスに登録することで収益性を大きく向上させる可能性がある
音楽配信のコストと収益性を考える
「配信にはお金がかかる」というのが、音楽配信サービスの利用を躊躇する大きな理由の一つですが、そのコストと潜在的な収益を比較してみましょう。
代表的なディストリビューターであるTuneCore Japanの場合、シングル1曲の配信は年間およそ1500円からとなっています。これは月に換算すると約125円。カフェでコーヒー1杯分にも満たない金額です。
一方で気になるのが収益面です。ストリーミングサービスの再生単価について、あまりハッキリと明示されていませんが、一般的に1再生あたり約0.5円と言われています(サービスによって異なります)。つまり、全ストアで合計3,000再生ほどあれば、年間の配信費用(1500円)を回収できる計算になります。

Tune Coreのようなアグリゲーターを介すことで世界中のリスナーに音楽を届けることが可能になる
3,000再生というと多く感じるかもしれませんが、55以上のストアで180カ国以上に配信されることを考えると、SNSでの適切な告知とYouTubeなどへの並行投稿を行えば、決して到達不可能な数字ではありません。
さらに、以下の点も考慮する価値があります:
- 楽曲の蓄積効果: 複数の楽曲をリリースすることで、カタログとしての価値が高まり、継続的な収益につながる
- 長期的な視点: 配信は一度設定すれば継続するため、長期間にわたって再生される可能性がある
- 予期せぬ発見: 思わぬところでプレイリストに追加されたり、アルゴリズム推薦されたりする可能性もある
TuneCoreの新サブスクリプションプラン

Tune Coreでは固定金額性で、多くの楽曲を登録しても価格が変わらないUnlimitedプランが登場した
2025年2月、TuneCore Japanは従来の1曲単位での課金に加えて、サブスクリプション型の新プランを開始しました。月額366円(年間4400円)で楽曲数無制限に配信できるこのプランは、活発に制作活動を行うアーティストにとって魅力的な選択肢となっています。
年間3曲以上リリースする予定がある場合、このサブスクリプションプランの方がお得になる計算です。また、最初は1曲単位で配信を始め、楽曲数が増えてきたらサブスクリプションプランに切り替えるという段階的なアプローチも可能です。
活動のフェーズに合わせて最適なプランを選択できるようになったことで、より多くのクリエイターが音楽配信を始めるきっかけになりそうです。
SNSと配信を組み合わせた効果的な戦略
SNSと音楽配信サービスの両方を活用する際の基本的な戦略を考えてみましょう:
1. コンテンツの差別化
- SNS向け: MV付き、解説付き、メイキング映像など付加価値のあるコンテンツ
- 配信向け: 高音質な音源、場合によってはSNSとは異なるミックスやマスタリングを施したバージョン
2. リリースのタイミング
- SNSで先行公開し、反応を見てから配信サービスにリリース
- または、配信開始日を告知して事前にSNSで話題を作り、当日に一斉公開
3. クロスプロモーション
- SNSでは配信リンクを、配信サービスのアーティストプロフィールではSNSリンクを掲載
- YouTube動画の説明欄に配信リンクを記載
4. リスナーとの関係構築
- SNSではコミュニケーションを重視
- 配信サービスではプレイリスト戦略を意識
重要なのは、どちらか一方だけを選ぶのではなく、それぞれの特性を理解し、補完的に活用することです。SNSでの活動はファンとの関係構築に、音楽配信はより広いリーチと収益化に、というように役割分担を考えると効果的です。
始めるなら今がチャンス:なぜ音楽配信をすべきなのか
音楽配信サービスの利用を考えるなら、今は絶好のタイミングです。以下が、特にSNSでの活動はあるものの配信はまだという方々が、配信を始めるべき理由です。
2. 新規リスナーの獲得: 音楽配信サービスには、SNSでは出会えない潜在的なファンがいる
3. プロフェッショナリズムの確立: 正規の配信チャネルでの公開は、アーティストとしての信頼性を高める
4. 著作権の明確化と保護: 自分の楽曲の権利を明確にし、保護することができる
5. 長期的な資産構築: 楽曲が増えるほどカタログ価値が高まり、継続的な収益源となりうる
特に、「別にお金を稼ぐつもりはないから…」と考えている方も、自分の楽曲をより多くの人に届ける手段として、また創作活動を続けるための資源として、配信による収益化を検討する価値はあります。
まずは最初の一歩を踏み出す
音楽配信を始めることに迷いがあるなら、まずは1曲だけでも試してみるという選択肢があります。すでにSNSで良い反応を得ている楽曲から始めれば、配信後もある程度の再生数が期待できるでしょう。
重要なのは、「配信か、SNSか」という二者択一ではなく、両方を組み合わせてより効果的に自分の音楽を届けるという視点です。インターネット上の選択肢が多様化する中で、クリエイターもまた多角的なアプローチを取ることで、より多くのチャンスをつかむことができます。
あなたの音楽は、より多くの人に届けられる価値があります。SNSでの公開に加えて、音楽配信サービスという新たな扉を開いてみてはいかがでしょうか。そこには、思いがけない出会いと可能性が広がっているかもしれません。
【関連情報】
Tune Core Japanサイト




コメント